前回、テレビボードを自作する上で必要な材料・道具・費用について書きましたが、今回は実際の手順について紹介していきたいと思います。
集成材を適切な大きさに加工する
私たちはタモの集成材でテレビボードを自作しました。
タモは強度が高く、我が家が床材として採用しているオーク材との色味の相性が良かったため、タモを選択しましたが、ホームセンターや材木店を探し回っても必要な大きさ・厚みのものがあまり無く、探すのに少し時間がかかりました。
ネットでは色々なものがあるので、比較的簡単に手に入るので楽だと思います!
が、木材にはそれぞれ個性があるので木目の出方であったり保管している環境によっては色味なども若干違ったりするのか…?と思うこともあり、実物を確認してから購入したいという思いがあり、ホームセンターで購入することにしました。
ホームセンターで取り扱いがあったサイズが、4200㎜×500㎜×25㎜のかなり長いサイズの木材なので、当然ながら自家用車にそのまま積んで帰ることができませんでした。
そこで、まずは集成材のカット・面取りをお願いしました。
店舗によっては細かな価格の差がありますが、上記のサイズの木材を1800㎜×430㎜×25㎜の大きさの板2枚、600㎜×500㎜×25㎜の大きさの板1枚に加工してもらいました。
ちなみに、600㎜×500㎜×25㎜の板については、予行練習も兼ねてサイドテーブルを作るのに使いました!
どんな仕上がりになるか試したくて作りましたが、サイドテーブルもなかなか良い出来で、リビングの雰囲気に合っていて個人的にとてもお気に入りです♪
なお、前回の記事でも書きましたが、板を加工するときの大きさについては使用する脚の大きさで決めると良いと思います!

どんな脚を使用するのか、事前にある程度決めておこう…!
加工してもらう時の費用と時間
ホームセンターで加工してもらう時の費用とかかる時間については、店舗により多少違うと思うので確認が必要ですが、私たちがお願いした3枚の板を切り出す+必要な個所の面取りで大体750円ほどでした。
加工に要する時間としては、私たちがお願いした店舗では専門の店員さんがいれば即日加工可能だったのですが、お願いした時には不在だったので翌日以降の受け取りということでした。
どちらにしてもそこまで時間のかかる加工ではないので、購入後すぐに加工し入手することができます。
・・・ここで私たちは自宅に木材を持ち帰るのですが、1800㎜の木材を2枚運べる自家用車を持ち合わせていなかったので、親族の車を借りてどうにか運ぶことが出来ました。

木材のサイズによっては自家用車に積めないこともある・・・!
ホームセンターによっては店舗で購入したものであれば、軽トラなどを貸出してくれるサービスもあるので、要確認です。
なお、加工をお願いして、翌日に引き取りに行くことができなかったのですが、事前に言っておけば店舗で保管してくれるとのことで、2週間ほど保管してもらいました!
まずは、とにかくヤスリがけ!
木材を手に入れてまずやることは、とにかくヤスリがけです。
もう、ずっとヤスリがけです…(語彙力)
木材を軽く水で拭く→ヤスリをかける
作業をする前に、必ずブルーシートなどを床に敷きましょう。
床が細かな木の粉だらけになります。・・・ブルーシートを敷いても木の粉だらけになりますが。
そして、マスクも必須です!
下準備が出来たら、ヤスリをかけていくのですが、木材が堅くてサンダーでヤスリをかけても全然ヤスリがけができない・・・!という事態に。
そこで、木材を軽く水拭きをしてからサンダーをかけると、木材の表面が柔らかくなる+表面の凹凸が分かりやすくなりヤスリがけがしやすかったです。

木材を濡らしてはヤスリがけ。その繰り返しがポイント!
正直、ホームセンターで購入できる集成材は、あまり気にならない人にとってはヤスリをかけなくてもいいんじゃない?と思うようなキレイな集成材が多いのですが、
手で触ってみると、ザラザラ感があり手触りがよくなかったり、集成材なので木目や節があり表面に凹凸があります。
何度も何度も水拭きをして、サンダーをかけて・・・という繰り返しの作業はとても大変ではありますが、ここで丁寧にヤスリがけをすることで、仕上がりがとてもきれいになります!!
ヤスリがけの目安
テレビボードを自作する上で難しいのは、どこまでの仕上がりを求めるのかということ。
それによって、ヤスリがけの回数が大きく異なってきますので、実際のヤスリがけの回数などについては自分でやりながら調整してください。
やろうと思えば、いくらでも手はかけられるし、手間をかけたくなければヤスリがけをしなくてもテレビボードの形にはなるからです。
ちなみに私たちは、せっかくお金と手間をかけてまで自作するのであれば自分たちが納得のいくキレイなテレビボードにしたいと思い、結構念入りにヤスリがけをした(方だと)思います。
100番から400番の紙ヤスリを順番に使用していくのですが、一枚の板につき裏表はもちろんですが、側面まで全てヤスリをかけていきます。
80→100→150→200→240→400のように、番号が小さい方から順番にかけていきます。

耐水ペーパーも準備したけど、実際は紙やすりだけで十分!
実際にやってみた印象としては、どの紙ヤスリもある程度同じ回数かけました。
が、実際にやってみて、どの木材を使用するのか、どこまでのクオリティを求めるかで使用する紙ヤスリやサンダーをかける回数などは異なってくると思うので、あくまでも参考程度に考えてください☆
実際、サンドペーパーを何枚くらい使用したのかは数えていなかったのですが、それぞれ10枚くらいは使ったのではないでしょうか…。
終始言っていますが、どの程度のクオリティのものを作るかで、このあたりの塩梅はだいぶ変わってきますので、実際に作ってみながら自身が納得できるところを模索してみてください(^^)/
木材が乾くのを待ち、毛羽立ちがないか確認をする
水で濡らしてサンダーをかけて、再び濡らして・・・を繰り返すと前述しましたが、そろそろいいかな・・・?と思った頃に、木材をしっかり乾かしてみましょう。
先に書いたように、木材を湿らせることによってサンダーをかけやすくなるのですが、その分木材の表面のヤスリがかかっているところとかかっていないところの差が出やすくなります。
濡らしていたときに表面が滑らかでも、実際にしっかりと乾燥させてみると表面に凹凸があったり、毛羽立ったように木材の表面がザラザラしていたりします。
きちんと乾かす前に次の工程である塗装をしてしまうと、凸凹していたりザラザラしたままの最悪の仕上がりになってしまいます。
木材が乾くまで時間はかかりますが、せっかく丁寧にサンダーをかけてもムラがあっては意味がないので、しっかりと確認をしてから次の工程に進みましょう。

サンダーをかけた面がしっかりと乾くまでの間に、側面や裏側などの他の個所のやすりがけをしておくと効率◎
すべての面のやすりがけが終われば、いよいよ塗装!
一番大切なやすりがけが終われば、いよいよ塗装の工程に入ります!
次回の記事にまとめますので、ぜひご覧ください(‘ω’)

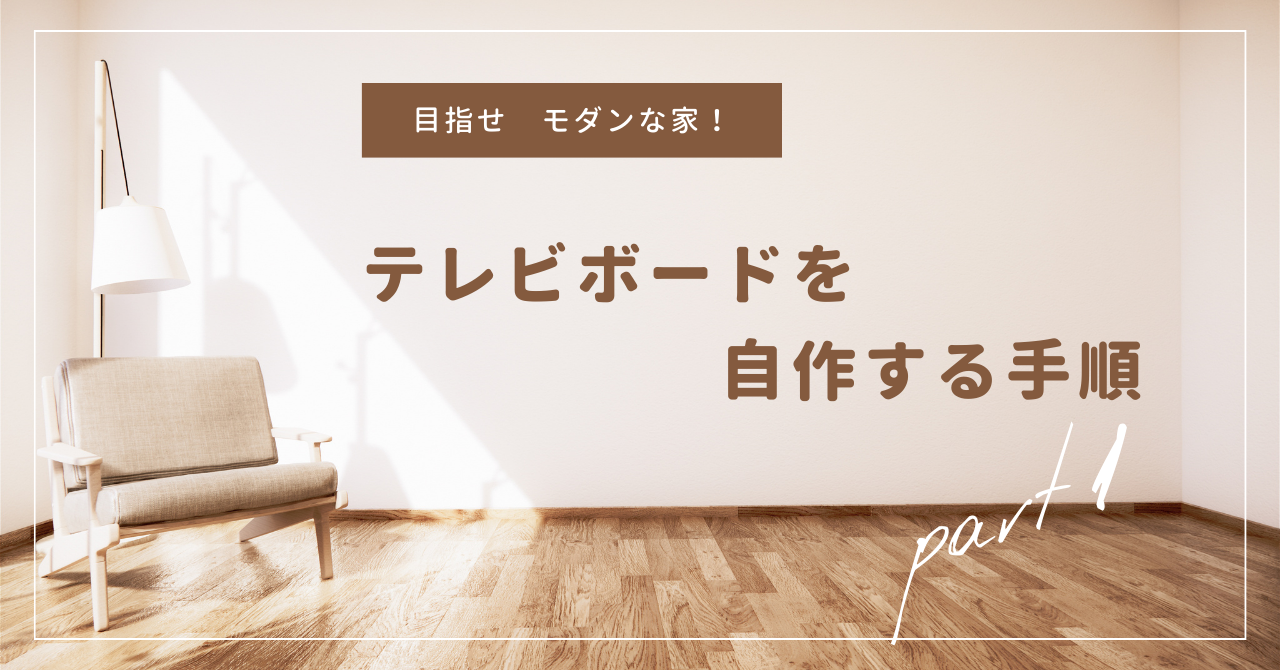
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d515555.84d12614.2d515556.a251339d/?me_id=1261122&item_id=10938825&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F030%2F4977292490030.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d849774.828f895c.2d849775.3f0f4e44/?me_id=1250757&item_id=11125235&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhatnot%2Fcabinet%2Fm%2F03%2F4962308794882-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント