前回、日除けや目隠しにも。タープでおうち時間を快適に!ということで、庭にタープをつけて良かったということを書きましたので、実際我が家はどのように設置しているのか紹介します!
前回も書きましたが、我が家では外壁にビス留め金具を使用して固定しています。

では、反対の受け側はどうしているかというと、
角材にアイプレートを取り付けてタープを固定できるようにしています。
結論:タープに高さを出すために角材を使用

画像のように、角材を使って高さを出してタープを固定するようにしました。
なぜそのような経緯になったかというと・・・
下の空間が狭くて有効活用できない問題
よくタープやサンシェードと検索して出てくる画像には、ペグを地面に打ち付けたり、ウエイトなどの重りを置いて地面に固定する画像が出てきます。

プールをしたり、テーブルとかを置きたい♩


・・・タープにある程度の高さを持たせないと厳しいよ

庭が広くて、タープも大きければできたのかな・・・
そのままタープを地面に降ろしてしまうと、有効活用できる空間が少ないのでどうにかできないか・・・と色々試行錯誤してみました。
フェンスに固定すると破損の可能性アリ
まずは、手っ取り早く出来る方法としてフェンスに固定してみることに。
この時にも、タープから伸ばしたロープをフェンスに固定するのではなく、角材をフェンスに固定からから、高さを出せるようにしてみました。
- 無風状態では問題なく使用可。
- 風がある状態では、フェンスに負荷がかかっている感じがする。
角材自体はタープを固定していても問題なさそうだが、フェンスがその力にいつまで耐えられるか。

万が一、フェンスが破損したら修理代もかさむし、近隣の家に迷惑をかける可能性もあるね

今すぐやめよう!!
見栄えも考慮して角材を使ってみる
そこで、フェンスなどに負担をかけないように角材が自立した状態でタープを固定できるようにしようと考えました。
見栄えと強度面から角材を採用。
角材よりも、単管の方が加工したり使用するには手間がかからず楽なのですが、単管は銀色で存在感もあるので庭に常設で置いておくには格好が悪いかな・・・と思ったからです。

単管は加工に手間をかけたくない人にはオススメ!
見栄えだけでいうと黒いプラスチック製のポールなどもあったのですが、長さが足りなかったり、細くてしなってしまい強度が足りないなどの問題があり、結局角材へと辿り着きました。
自立するポールの作り方
①角材に、ロープ固定用のアイプレートを取り付ける
まずは、角材の下準備としてロープを固定するためのアイプレートを取り付けます。
単管を使用する場合には、ジョイントパーツがあるので、これを取り付けるだけで済みます。

パーツを組み合わせるだけなら、知識や技術がなくても楽チン!
②ブロックに、土台となる部分のセメントを流す
ではいよいよ、土台となるブロック留め具にコンクリを流していきます。
我が家が使ったのは、このような四角い形のブロック。
形はどうでも良いのですが、角材が入れば良いので何でもオッケーです。
ちなみにブロックはホームセンターの方が安価に手に入ると思います。
ちなみに単管の場合は、単管ブロックを使うとこれまた手間が省けます!
我が家と同じようにキューブ型のブロックを使用する場合には、このままだとブロックと角材は安定しないので、セメントを流し込んで固定していきます。
これも近くのホームセンターなどで手軽に入手できると思います。
ブロックに流し込むときには、3回に分けて流し込みます。
まず第一の工程は☆印の部分。
- 雨水の水抜き穴用ストローをブロック中央部分に固定する ☆
- (ブロックの深さにもよるが)4分の1程度流し込んで土台を作る ☆
- 適当な木材などを使って、流し込んだセメントを転圧する ☆
- ブロックいっぱいになるまで、セメントを流し込む→転圧→乾燥を繰り返す(以下の③と④の工程を参照)

しっかりと転圧することで、より丈夫で割れにくくなりますよ
真夏に作業して、丸一日で乾燥しました。
私たちは、雨水の水抜き穴を開けずにブロックを作り上げてしまったのですが、やってみたあとに

この工程で水抜き用の穴を開けておくべきだった・・・!
と後悔したので、皆さんはぜひ水抜き穴を確保してから作ってみてくださいね!
角材や単管を地面に埋めるので、雨水などがたまってしまう可能性があります。
角材や、ブロックの中に水がたまっている状態では衛生的にもよくないので水抜き用の穴として太めのストローなどをセメントを流すときに一緒に置いておくことで簡単に穴を開けておくことができます。
私たちは後でインパクトドライバーを使用して穴を開けたのですが、この時点で穴を開けておけば面倒くさい手間を省くことができますからね。

インパクトドライバーがある人は、どちらでもOK!(面倒だけど)
③角材を固定して、セメントを流す
一度目に流した土台用のセメントが固まったら第二工程。
- 雨水の水抜き穴用ストローをブロック中央部分に固定する
- (ブロックの深さにもよるが)4分の1程度流し込んで土台を作る
- 適当な木材などを使って、流し込んだセメントを転圧する
- ブロックいっぱいになるまで、セメントを流し込む→転圧→乾燥を繰り返す ☆
いよいよ二回目のセメントを流し込みます。
この時に、4分の3程度まで流し込むのですが角材を固定してからセメントを入れます。
ブロックの中央に角材を置いたら、小さく切った木材などを空いたスペースに入れ、木材同士で突っ張るようにして角材を中心に固定するようにします。
木材に触れない程度のところまでセメントを流し込んだら、再び転圧をしてから乾燥させます。
ここでも一日でだいたい乾燥が終わりました。
④留め具を入れて、セメントを流す
角材がある程度固定されたら、最後のセメントを流し込んでいきます。
- 雨水の水抜き穴用ストローをブロック中央部分に固定する
- (ブロックの深さにもよるが)4分の1程度流し込んで土台を作る
- 適当な木材などを使って、流し込んだセメントを転圧する
- ブロックいっぱいになるまで、セメントを流し込む→転圧→乾燥を繰り返す ☆
この時に、(タープを使用しないときの)ロープを固定する金具を一緒に入れておくと、普段の使い勝手がよくなると思います!

そして、このネジフックをセメントで固定するときにも、ネジフックをそのまま入れてしまうと引っ張られたときに引き抜かれてしまうかもしれないので、ネジフックを木材に刺して固定してから、セメントで固めるとより強度が出ます。

風があるときには、ロープが揺れてカチャカチャ鳴るので、ネジフックで固定しておいて良かった☆
地面に埋めたら完成
さて、いよいよ出来上がった角材を庭に設置していきます。
埋める部分に大きな石があり、苦戦
我が家は外周にまわしたメッシュフェンスに沿って角材を立てることにしたのですが、庭に埋めるにはブロックがしっかりと埋まる程度の深さの穴を掘る必要があります。
実際に穴を掘ってみると、大きな石があり、穴を掘るのに少し苦戦しました・・・!

その他にも、庭の造りによってはフェンスなどの土台としてコンクリがあったり、配管などの問題で深くまで掘れない場合もあると思いますので、ポールを設置しようとする場合には、どこなら深く掘っても大丈夫なのか予め検討しておきましょう!
掘り起こしたあとは、水できちんと固めて
ブロックがしっかりと埋まるような穴を掘ると、思いのほか土が出てきます。
全て元の場所に戻すことはできないと思いますが、出来るだけ土を戻さなければ時間が経って雨などで浸食されたときにブロック周辺だけ土が足りない!なんてことになりかねないので、しっかり埋め戻しましょう。
ブロックを地中に入れて、土を周りに敷き詰めた後、シャワーなどで何度か土を湿らせてから転圧すると、より良いです。
後ろに傾けて設置すれば良かったと反省
我が家は設置したあとに、

タープで引っ張られるのを考えて、逆方向に傾けて設置すれば良かった~!
と少し後悔しました。
現時点で、真っ直ぐに立てていても途中で倒れてきたり、徐々に傾いてきたり・・・ということはないのですが、これから設置を考えている人は、気持ち後ろに傾けて設置すると良いかもしれません。
人工芝、防草シートをカットして埋めたが、問題なし!
外構の工事が終わってしばらくしてからポールを設置することにしたので、庭にはしっかりと人工芝が敷いてある状態の我が家。
ポールを設置するにあたって、地面を掘り起こさなければならないので、人工芝や防草シートを剥がしたらきちんと元に戻せるのか?!と思いましたが、カッターで必要最低限の切れ込みを入れて穴を掘ったりしましたが、最終的にはきれいに戻すことができました!

まとめ
今回はタープを出来るだけスタイリッシュに設置するために自作した方法について書いてみました。
乾燥にそれぞれ一日かかることなどを考慮すれば、材料を揃えてから4~5日あれば制作・設置が可能です。
ネットなどで材料を買いそろえれば、単管でもブラック等あるのでスタイリッシュになりそうですが、今回はホームセンターなどで手に入るものでお値段を抑えつつ作ることができました。
今回は2mの角材を使って自作してみましたが、更に高さのある角材やポールを使えばタープ自体も高い場所で固定できるので、より圧迫感なく庭で過ごすことができます。
我が家は2.5m×3mのタープを使用していますが、タープ自体ももっと大きなものにすれば、より快適になりそうです。
前回の記事についてはこちらをチェックしてください。



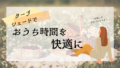

コメント